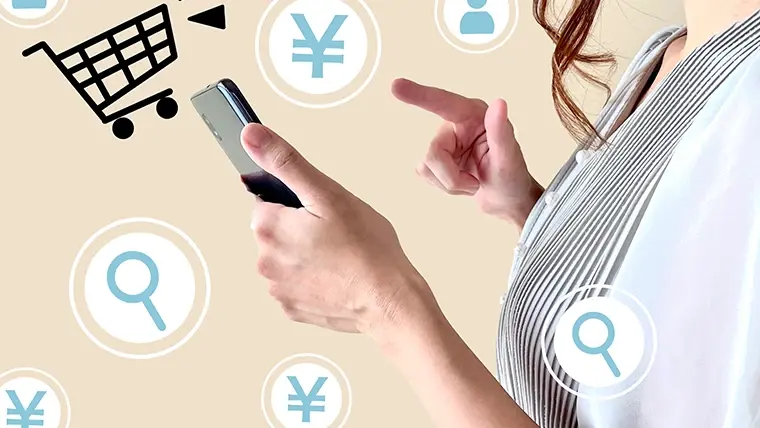スマートフォンの普及や私たちの生活スタイルの変化により、ECサイトでの買い物はより一層生活に浸透しています。
購入したものがすぐに届いたり、とても便利なECサイトですが、その裏には洗練されたECサイトの仕組みや整えられた物流が存在しているのです。
この記事では、ECサイトの基本的な知識を踏まえながら、ECサイトと物流の仕組みをわかりやすく解説していきます。
ECサイトとは?
ECサイトとは、インターネット上にあるWebサイト型の店舗のことです。
そもそもECはElectric Commerceの略称で、Eコマースと呼ばれることもあります。また、ECは電子商取引を意味し、企業同士がEDIで行う受発注など、消費者がWebサイトを通じて行う買い物以外の取引も含まれます。
ECサイトには、商品・サービスを販売する企業自体が運営する自社ECサイトと、複数の企業が出店しているモール型ECサイトがあります。
有名なECサイトとしてAmazonや楽天があります。最近は、モール型ECサイトに出品しなくても誰でも簡単にECサイトを制作できる、BASEやShopifyといったサービスもあります。
ECの市場規模

参照:経済産業省「令和5年度電子商取引に関する市場調査の結果を取りまとめました」
2023年のBtoC-ECの市場規模は、24兆8,435億円でした。前年の2022年と比べておよそ2兆円も増加しています。
2014年の12兆7,970億円と比べても倍の規模となっており、かなりの成長傾向にあります。特にコロナ禍だった2021年・2022年に20兆円を超えており、ECサイトの価値がさらに高まりました。
ECサイトの市場規模は年々増加傾向にあるため好調な市場であり、今後も多くの企業の参入が見込める活発な市場と言えるでしょう。
日本におけるECサイトの歴史
日本におけるECサイトは1990年代からはじまり、急速に進化をしてきました。
1997年に楽天市場が開設され、モール型ECサイトとして注目されました。1999年にはAmazonが日本市場へ参入し、この頃から本やCDなどカテゴリー特化のECサイトが増えました。
2000年代に入ると、クレジットカードや物流の普及によりさらに市場は成長しました。
Yahoo!ショッピングが開設され、楽天市場と並び代表的なECサイトになりました。他にはZOZOTOWNやヨドバシドットコムなどファッション、家電に特化したサイトも展開されています。
2010年代では、スマートフォンの普及やグローバル化の加速によってさらにECサイトの間口が広がりました。
メリカリに代表されるCtoCのプラットフォームや、サブスクサービスの登場も特徴的です。
2020年代になるとコロナ禍の影響でECサイトの需要がさらに増加しました。ライフスタイルの変化により、ECサイトはより私たちの生活に入り込んだのではないでしょうか。
また、インフルエンサーや有名人が商品を動画や配信で紹介するライブコマースも人気があります。
注文から配達までの仕組みと流れ

ECサイトでの買い物
消費者がECサイトで商品を選び、カートに追加します。
その後注文画面へ進み、配送や支払いに必要な情報を入力していきます。支払いはクレジットカード、代引き、銀行振込などいくつかの方法を選べるのが一般的です。
必要な情報を入力した後、注文を確定させるとECサイトのシステムが注文データを受け取ります。配送までに間に合えば、通常商品のキャンセルも可能となっています。
ほとんどの場合、注文した後すぐに受注確認メールが自動的に送信されます。ECサイト側は商品の受注を確認し、ピンキングと発送処理へ進みます。
ピッキング・発送
倉庫の従業員、あるいは自動ロボットが注文の商品を棚からピッキングします。ピッキングとは、注文された商品を集めることを意味します。
ピッキングした商品に誤りがないか、破損がないか検品を行い、配送時に商品が傷つかないように梱包も行います。
その後、配送に必要な住所などの情報が記載されたラベルが発行され、梱包済み商品に取り付けられた後発送されます。
配送・配達
ECサイトの倉庫から発送された商品は配送業者によって消費者の元へ配送されます。
配送業者は各地域にセンターを設けていることが多く、商品の配送先ごとにまとめて仕分けし、配送先の地域に近いセンターへ送ります。
さらに、その地域センターでエリアごとに細かく配送担当者に割り当てを行い、商品が配送されます。
最近のECサイトでは発注からお届けまでのスピードがはやいのは当たり前のような流れですが、そのためには配送が重要な役割を担っています。
お届け
最終的に商品は消費者のもとへ届けられます。
配達完了までの間に追跡番号から配送状況をリアルタイムで確認できたり、配送日もあらかじめ決めることができるなど、消費者の生活に合わせた配送が可能となっています。
お届け時には受け取りのサインをすることが多いですが、最近はポストへの投函や置き配といったように消費者と配送業者が接触しないお届け方法も選ぶことができます。
以上が注文から配達までの流れです。ECサイトごとで多少の違いはあるかもしれませんが、基本的にはこうした流れになっています。
ECサイトと物流のポイント

倉庫・拠点の用意
ECサイトの開設や運営において倉庫・拠点をどうするかということは重要なポイントであり、多くの場合課題となり得ます。
欠品しないように商品を潤沢に用意しておくための場所は必要ですが、費用や場所の確保の問題など、クリアすべき問題が多いからです。
そうした課題を解決するために、十分なスペースがなくてもECサイトの倉庫を利用し、商品の保管から発送・返品対応まで依頼できるフルフィルメントサービスといった方法を選択できるECサイトもあります。
また、商品を倉庫に保管せず、入荷した商品をすぐに出荷するクロスドッキングという流通方式も最近は注目を浴びています。
ピッキングの効率化
人手不足が叫ばれる今、ピッキングの効率化も大切です。
最近はダークストアという倉庫型店舗が増えています。実店舗としては運営せず、オンライン注文専用の倉庫として利用します。
小規模のスペースで作業を行うため、ピッキングや配送にかかる時間の短縮と効率化を図ることができます。コロナ禍でお店が閉められて空きスペースとなった場所を利用することが多いです。
配送業者の役割
ECサイトの発展には配送業者が欠かせません。ECサイトと消費者を繋ぐ重要な役割を担っています。
特に最近は物流の最終拠点から消費者までの配送が注目されており、ラストワンマイルとも呼ばれています。

ラストワンマイルをどう改善していくか様々な企業が力を入れていますが、消費者の自宅に商品を届けるのではなく、小売店などに置かれたロッカーに商品が届き、消費者がそれを取りに行く方法もよく利用されます。
そうした方法は、BOPIS(Buy Online Pick up In Store)やクリック&コレクトと呼ばれ、お届け時の不在による再配達問題を減らし、消費者のライフスタイルに合わせた配達が可能になります。
SDGsとサステナブル物流

ステナブルな物流で環境負荷を減らしつつ効率的な配送を実現するために、様々な取り組みがなされています。
今回はその中から代表的な3つの取り組みをご紹介します。
電動配送車
電動配送車を導入することによって、物流の脱炭素化を推進することができます。
走行中のCO2排出量が通常の車と比べて大幅に削減できるため、CO2排出の削減になります。また、静音性も優れているため騒音を防ぐことができ、ガソリンより電気の方がコストの安定性があって燃料コストの削減にもつながります。
日本ではヤマト運輸や佐川急便が都市部で導入を進めており、海外ではAmazonが電気自動車メーカーと提携して電動配送車を開発しました。
まだ車両価格が高いため導入コストが高い、充電ステーションが不足している地域もあるためインフラが整っていないといった問題や課題もあります。
再生可能エネルギーの活用
再生可能エネルギーを物流に導入することによってサプライチェーン全体の環境負荷を減らすことができます。
倉庫やセンターに太陽光発電パネルを設置することで、施設の電力を自社で供給する取り組みを行っている企業があります。
先述した電動配送車も再生可能エネルギーを活用することができ、太陽光や風力で発電した電力を車に充電することもあります。
エコ包装
エコ包装に取り組むことで、資源の無駄や廃棄物を減らすことができます。
再生紙やバイオプラスチックを原料にした包装資材の採用や、プラスチック使用量を最小限に抑えた緩衝材、封筒が導入されています。
また、配送後に包装資材を回収し、再利用して別の包装資材の原料とする取り組みも行われています。
中部流通のエコ包装の取り組み
実際に当社でもお客様の店舗で排出された不要な段ボールを回収し、封筒へリサイクルするという取り組みを行っています。
そちらの取り組みを紹介した記事もございます。ぜひ、下記リンクよりご覧ください。
まとめ
ECサイトと物流の仕組みをわかりやすく解説!注文から配達までの流れやSDGsの観点から見た物流などをご紹介します
とても便利なECサイトですが、その裏には洗練されたECサイトの仕組みや整えられた物流が存在しているのです。
注文から配達までは通常、ECサイトでの買い物、ピッキング・発送、配送・配達、お届けの流れで行われます。こうした仕組みづくりで特に重要なのは、拠点の用意、ピッキングの効率化、配達業者の役割です。また、最近はSDGsに適したエコ包装を心がける取り組みも盛んになっています。
キーワード
- ECサイト
- 物流
- サステナブル